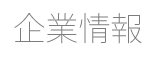『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』
『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』
M. ザネッティ、F. パルメジャーニ 訳:鈴木鉄忠、大内紀彦
岩波書店|2016年9月13日刊|2,700円+税
イタリアには、かつてマニコミオと呼ばれる巨大な精神病患者収容施設が多数あった。それがフランコ・バザーリアという名の精神科医が1961年に北イタリア・ゴリツィアの州立精神病院長に赴任し、隔離入院からコミュニティの中での精神医療サービスへと大胆な改革を進めてから、山が崩れるように精神医療のパラダイムが変わった。1968年には精神病院縮小の立法措置がとられ、1978年には通称バザーリア法として知られる精神医療改革法と「国民保健サービスの制度」に関する組織案が整備され、新たな入院、新しい精神病院の設立が禁じられ、各州に対して精神病院を漸進的に廃止する責任が課せられた。そして幾多の抵抗に遭いながらも1998年には全てのマニコミオが機能を停止し、2000年にはイタリア全土から精神病床が消えたのである。
これはたんにひとつの国の医療政策と呼ぶにはあまりにも大きな出来事である。「狂気」を社会がどう受容するかという意味をもった、いわば文明史的な出来事と言ってよい。
日本では、統合失調症の長期入院が、依然として当たり前なのであるが、このイタリアの歴史的事件に、世界一の精神病床を擁する日本を対比したのが、大熊一夫による『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』(岩波書店、2009)である。この彼我の違いは、いったい何なのだろう。大熊のイタリアルポの部分を改めて丁寧に読み返せば、それなりに書かれてはいるのだが、ここでみるべきものは、精神病院から地域精神保健サービスへというような、精神科医療の在り方として語りうる種類の問題ではない。
ジャーナリストのF・パルメジャーニとバザーリアとともに闘ったトリエステの政治家M・ザネッティが、行動する知識人バザーリアにフォーカスしてその経緯を書いたのが、この本である。
バザーリアは…
「鋭い社会学的な関心を抱き、広い意味での政治的なアンガージュマン(政治的参加)を実践した。…専門家という枠組みから抜け出し、社会に対する普遍的な視点を獲得することができた。」「黒人精神科医フランツ・ファノンが強靱な意志で一切の妥協を拒みつつ示したことは若き研究者バザーリアに多大な影響を与えた。」「彼が行ったことは実質的には『新たな精神医療の提案というより、市民としての告発』だった。」
彼は、ゴリツィアの任期が終わる頃に『否定された施設——精神病院からの報告』を出版している。文字通り『否定された施設』は、オルタナティブ精神医療の提案として、幅広い賛同者を得た。施設では拘束衣を廃止し、医師たちは白衣を脱いだ。施設内では普段着の医療者と収容者がともに自治集会を開いた。しかし、バザーリアに対する反発もすさまじかった。マニコミオを反社会的な「革命のための巣窟」にしようとしているという告発、入院患者が妻殺し事件を引き起こしたために、バザーリアも管理責任を問われて裁判にかけられたが、このときはヨーロッパの精神医学の重鎮たちが彼を支援した。この事件でバザーリアはゴリツィアから身を引くことになる。
わが国でも、1970年代には精神障害者に対する保安施設への強制収容(予防拘禁)を定める刑法改正が論争の的になっていた。大熊は、朝日新聞に連載した『ルポ・精神病棟』(朝日文庫,1973年—リンクは復刻版)で、精神病院医療の悲惨を描いた。
バザーリアは、米国、イタリアのパルマを経て、トリエステの精神病院の院長になると、後に伝説となるような精神病院改革を始めるのであるが、その根本的なモチーフについて、著者等は『エスプレッソ』紙のインタビューを引用して次のように紹介している。
「狂気とは、深い苦しみに裏打ちされた表現なのです。…『苦しみと向き合う』唯一の方法は、…患者のみならず…、当事者と関わりを持つ者すべてが、責任の一端を担い、患者がその苦しみに耐えられるよう支援する。そうすることで本人の負担を軽くしてゆくのです。」(インタビュー、1978年6月)
バザーリアは、狂気はコミュニティで受け容れるべきもので排除すべきものではないという、至極当然でありながら近代社会において許容されなくなってしまった事態を、確実に戦略性をもって覆したのである。
看護師組合は猛反発するが、バザーリアは県の行政当局を味方に乗り切る。医師たちから押しつけられる手に負えない患者を一人で喜んで引き受け、重症の患者に仕事を与えて仲間にしてしまう。
この時期、トリエステには世界中から異議申し立てをしてドロップアウトした医師や看護師たちが集まった。トリエステは「自らの社会的責務と職業的使命を果たす可能性をもちえたヨーロッパで唯一の場所だった。」マニコミオの「巨大な鉄格子の扉は開け放たれ」患者達は自由に行き来した。「<狂人>たちが町へ「侵入」を始め、さらに町が狂気を受け容れ始めた。」もちろん幾多の抵抗があったわけだが、他方、いくつかの奇跡的な出来事もあった。
この艱難辛苦の感動物語は、映画「むかしMattoの町があった」(M. トゥルコ監督,2010年)で愉しむことができる(上映運動が続けられてきたが、『精神病院はいらない!:イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子3人の証言』(大熊一夫編著、現代書館)の付録DVDとなっている)。
そして患者たちが職を得て地域社会に復帰する仕組みづくりによって、この歴史的事件は現実のものとなったのである。
このイタリアの制度は、専門家によれば「精神病院の閉鎖により生み出された先進的な地域精神保健システムやリハビリテーション技術によるだけではなく、むしろ国民性や文化性に支えられている」(水野雅文)。実際、巨大なマニコミオが公的に維持されてきたイタリアと老人病院化しつつある私立精神病院の多い日本を比較して云々するべきものではないのだろう。
本書では、バザーリアのイタリア共産党との緊張関係、労働者アウトノミア運動との関係、そしてR.レインやD. クーパーなど反精神医学グループ、同じく急進派G. ドゥルーズやP-F. ガタリらに対するバザーリアの姿勢についても、断片的ながら言及されている。(評者:秋元秀俊)