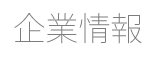失われてゆく、我々の内なる細菌
失われてゆく、我々の内なる細菌
マーティン・J・ブレイザー 山本太郎訳
みすず書房|2015年7月1日刊|3,200円+税
人体にはヒトの細胞の3倍以上に相当する、100兆個もの細菌が常在している。そして、子宮内には常在菌は(ほとんど)ないと考えられている。ということは、100兆個もの細菌というのは、生まれてから(出産の過程を含め)、我々の体内に入り込み、共生するに至った、と。つまり、それらの細菌は、手渡し、口移し、スキンシップ、(下水の設備によって差はありますが)糞便、、等々で、先祖代々継ぎ足しの秘伝のタレが如く受け継がれてきたものなのである。これだけで、人類史、いや、生物史の妄想がムクムクと取り留めもなく膨らむが、これはあくまで本書の前提に過ぎない。
本書の問題意識は、その脈々と受け継がれ、共生の過程で変化し続けてきたヒト体内のマイクロバイオームが、ここ数十年で危機にさらされていること、そして、そのことによる人の健康への影響にある。ヒト体内の細菌の多様性が失われている原因は、ヒトや家畜、農作物への抗生物質(の過剰使用)、先進国においては上下水道の発達といった環境の変化にあると考えられるが、ブレイザーは、抗生物質の使用自体を否定するような「トンデモ」ではない。寧ろ、自身が抗生物質によって一命を取り留めたエピソードを交え、現代医療において、抗生物質がなくてはならない武器であることを強調している。つまり、掛け替えのない武器だからこそ、その効力を失わないために抑制的な使用がいかに重要かを説いているのである。
さて、長くその微生物学の第一人者の研究対象になってきた細菌の一つが、ピロリ菌である。
日本では「ピロリ菌除菌」が「胃がん撲滅」の旗印の下にすすめられてきた。その過程で、2013年2月に、ピロリ感染胃炎の除菌に保険が適用された。つまり、ピロリ菌にとっては、今の日本は住み心地悪いことこの上ない。
「ピロリ菌? あぁ、胃炎とか胃潰瘍の原因菌ね、悪玉なんだから除去して当然でしょ」と思うかもしれないが、ブレイザーはピロリ菌除去のブームには乗らなかった。ひとつには、ピロリ菌が「ヒトと付き合いの長い菌」であること、さらには、ピロリ菌の保菌者の一部しか潰瘍を発症しなかっただけでなく、発症する人にも胃炎の症状が収まったりまた再発したりという長期のサイクルがあったためである。その後、研究を進め、ピロリ菌はヒトにとって、害ばかりでなく利益についても明らかになってきたのである。
「歳をとれば、ピロリ菌は胃がんや胃潰瘍のリスクを上昇させる。一方で、それは胃食道逆流症を抑制し、結果として食道がんの発症を予防する。ピロリ菌保有率が低下すれば、胃がんの割合は低下するだろう。一方、食道腺がんの割合は上昇する。古典的な意味でのアンフィバイオーシス(二つの生命体が、状況に応じて共生的にも規制的にもなる関係を築くこと—p.116)である。」(p.142)
つまり、ピロリ菌除去による胃がん撲滅(より正確には、胃の疾患の抑制)には「トレードオフがある」ということである。このトレードオフは、胃と食道という隣接する器官のもので少し視野を広げることで把握できそうではある。が、ブレイザーの真骨頂は、そこからさらに飛躍するところにある。消化器への影響に留まらず、喘息やアレルギーとの関連にまで視野を広げてしまうのである。その詳細は本書をお読みいただくとして、ここで示唆されるのは、エンドポイントを特定の疾病による障害や死亡(あるいは特定の臓器の機能)に据え置いていると、このようなトレードオフは見落とされてしまうということ。いや、そもそも、急性の疾患ではないものや(無症状・無自覚のピロリ菌保有者に対しする処置のような)予防的介入を行った際に、その影響が長い時間を経て出現する場合、そういったトレードオフは見落とされがちになるのは、自然なことのようにも思える。これは、急性かつ重症化しやすい感染症の原因菌と常在菌を同列に扱うことの危うさと云えるかもしれないし、現代の疫学研究において「特定の疾病による死亡率での検証ではなく、全死亡率で検証するべきである」という正論にも通底するものがあるだろう(※1)。
もちろん、昨今問題になっている薬剤耐性菌についても、15章の<抗生物質の冬>(抗生物質の春、あるいは、「マイクロバイオームの冬」の気がするのですが・・・)で詳しく取り上げられている。しかし、ブイレザー氏は耐性菌の増加だけを抽出して問題視するのではない。耐性菌が次々に生まれる環境とは、すなわち、耐性菌が跋扈しやすい環境でもある。抗生物質を服用することにより、耐性菌が生まれる過程では、必ず、常在菌の細菌叢は単純化し不安定になっているのである、つまり「感染に対する感受性」が増大するのである(p.213)。
「私が心配しているのは、抗生物質が効かなくなるということだけではない。それだけではなく、内なる生態系崩壊のために、無数の人々が病気に罹患しやすくなる。そのことを心配しているのである。この二つの出来事は、関連しながら進んでいる・・・(p.221)」
ところで、我が家の二歳児は、昨日もジスロマックを処方された(普段はメイアクトが多い)。熱が上がったり下がったりが4日ほど続いて、両親はマイコプラズマ肺炎かもしれない、と心配していた。優しい元大学病院勤めだったと思われる小児科医は「どうやら肺炎の心配はなさそうだけれど」と言いつつ、心配性の親を安心させるために、「念のため」ジスロマックを処方した——もちろん、憶測に過ぎないが。その小児科医は、患者の(親の)話に耳を傾け、説明も丁寧だし、悪い医師とは思えないそうだ(僕も話を聞く限り「いい先生」だと思います。結局ジスロマックは飲ませていない僕は「身勝手で頭でっかちな親」なのかもしれませんが・・・)。少なくとも僕の近所では、そんな、善意による「取り敢えず、抗菌薬」の処方は、まだまだ続きそうである(※2)。
なぜなら、「医療制度は保険や政府からの支出によって維持されている。精度そのものは医療行為を行うためにあるのであって、行わないためにあるのではない。さらに製薬会社は、少しの新規投資、もしくは全く新規投資無しで巨額の利益を得られる現状に満足している」(p.226)からだ。ただし、ブレイザーは数々の解決策を提示しつつ近未来を予測する。
「現在、訴えられる恐怖というのは、何かを「しない」ことで訴えられる恐怖である。レントゲン写真を撮らなかった、抗生物質を投与しなかった、帝王切開をしなかった、といって訴えられる。しかし将来的には、不必要で正当化できない行為を行ったことで訴えられる恐怖が生まれるだろう。恐れは、最も有効な平衡装置である。」(p.232)
これは訴訟社会アメリカでの未来予測で、日本で同じようなことは起こらないだろう。訴訟以外の抑制装置が必要だが、今のところ一市民として個人的にできることは、抗菌薬嫌いの薬剤師の母に我が子に口移しで食べ物を与えてもらうこと(歯周病が気にならないでもないが)、子どもを小児科に連れて行くときに、無闇に医師をせっつかず、さりげなく、しかし気付いてもらえるように本書を小脇に抱えておくくらいのことである。ということで随分と長くなってしまったが、医療従事者の方だけでなく、僕のような一般市民にも(読みやすい! 翻訳も素晴らしい!)オススメの1冊である。
※1(この点は岩田健太郎氏の『ワクチンは怖くない』(光文社 2017)」でも議論されています、もっとも岩田氏は「全死亡率の希求」は正論であるが「やや理不尽」としていますが・・・。)
※2抗菌薬の一人当たり消費量は、日本は飛び抜けて多いわけではないが、広域スペクトルの抗菌薬の消費割合が多いことが問題視されている。また、消費量については、一人当たりの消費量が減っている中で、欧州は2010年、日本は2013年のデータで比較されている点は留意が必要である。
【薬剤耐性(AMR)の現状及び 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(p.7)】
(評者:秋元麦踏)