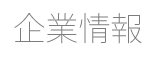中動態の世界 意思と責任の考古学
中動態の世界 意思と責任の考古学
國分功一郎
医学書院|2017年4月1日 刊|2,000円+税
私たちは、中学の2年ごろの英語の授業で初めて受動態というものに出会う。それまで、母国語のなかで意識しなかった態(voice)というものを学ぶ。また時制(tense)というものを学ぶ。そして、否応なく翻訳文で、ものを考えるようになる。こうして主に日本語しか読めないものの教養は、翻訳文によって涵養されるのである。
たとえば日本語の「られる」という助動詞は、受動・可能・自発・尊敬の四つの働きをもつが(本書中でも重要でない文脈で軽くこのことに触れている)、最近、新聞記事のようなプロの文章でも、そのいくつが曖昧に混在した気持ちの悪い文を見ることが多い。敬意を示すべき文脈でないところで、自発の装いで敬意の表明を感じさせる。しかし、これを気持ちが悪いと感じるのは、評者が凡庸に、能動と受動を主体からみた行為の方向の違いだと勘違いしているからかもしれない。じつは、この気持ちの悪い文章こそが本来の日本語なのかもしれない。元来、日本語の特徴は主語の欠如にあり、述語の曖昧性にある。能動と受動は、行為の方向ではなかったはずだ。
最初に態(voice)を教えるときに、スピノザについて國分が読み解くように、能動と受動は主体からみた行為の方向ではなく、行為の質の差であると教えられたら、どうだったろう。
日本語の意思には、自由な意思など、露ほどもなかった。最近はやりの「忖度」などということは、日本人のすぐれて一般的な態度なのである。これを哀しいと感じるのは、翻訳文化で育てられた戦後的教養に毒されているからなのである。
『中動態の世界』は、ひと言で言えば、「文法(グラマー)で哲学を解き明かす」というような哲学の中に閉じた議論をしながら、読者を『意思と責任の考古学』に誘う不思議な哲学書である。これほど淡白に平易に書かれた哲学書も珍しいが、読者が自分なりの読み方を愉しむことが出来るという意味で含蓄のある哲学と言える。
かくして、現象学の若手研究者の新刊書(串田純一著『ハイデガーと生き物の問題』法政大学出版局)のオビに「國分功一郎氏イチ推し!」と大書されるほどに、哲学者・國分功一郎氏の名前はキャッチーになっているらしい。
法律は、能動態と受動態で書かれているが、日常世界はいわば中動態なのである。政治は、大声の能動態と受動態で語られるが、生活者の世界はいわば中動態なのである。
評者は下世話な世界の住人なので、このように読むが、著者國分功一郎氏は決してこのようには書かない。これに似た文脈を探すとしても「完全に自由になれないということは、完全に強制された状態にも陥らないということである。中動態の世界を生きるとはおそらくそういうことだ。」(p.293)という一文が見つかるくらいである。「意思と責任の考古学」は、土にまみれた発掘現場には足を向けない、書物の発掘作業である。
依存症の患者は、意思が弱いのではない。意思とは強いとか弱いとかというものではない。精神病の専門家は國分功一郎の自由意思の説明に出会って、ふだん自分たちが感じていた言葉にできないもどかしさを、目の前で種明かしされたような経験をした。しかし、同調圧力の強いこの社会で、自由意思というものの価値を軽く見積もることはどういう意味をもつのだろう。気分は楽になるだろうが、果たして楽になればいいものなのだろうか。
『暇と退屈の倫理学』で“暇人”の効用を説いた國分は、暇人であることを “ぼんやりとした退屈に浸っている”状態の大切さとして哲学的に位置づけたことで、精神医学の専門家から高い評価を受けた。“ぼんやりとした退屈に浸っている”状態は、だれもが浸っていたい状態だが、しかし経済的に苦しく忙しいときに、自分の夫や妻が“ぼんやりとした退屈に浸って”いるとしたら、果たしてそれを尊重するこころの余裕が、評者にはあるだろうか。間違いなく、ない。ケアするものは、つねに優しくなければならない。“ぼんやりとした退屈に浸っている”妻に、本心からいい時間を過ごしているねと言えなければいけない。それを支えるためには、 “ぼんやり”なんかしていられない。暇なくせっせと働きつづけなければならないのだ。
著者は、哲学を態(voice)で腑分けするというアイデアを、端正に展開するところからほとんど一歩も外に踏み出さない。淡々と、言葉が言葉を引き出すようにストイックな解説に留まり、著者はその議論に今日的な意味を加えない。
それにもかかわらず、この哲学書が羽根を付けて羽ばたくところに、編集者白石正明のマジックがある。評者自身、もし医学書院のシリーズ「ケアをひらく」の1冊でなければ、この本を手に取ることもなかったろう。それほどに、編集者・白石正明氏の仕事は刺激的であり、問題提起的である。
(秋元秀俊)